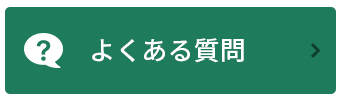ピロリ菌について
ピロリ菌(正式にはヘリコバクター・ピロリ菌)は、胃の中に住む細菌です。原則感染は子供の時に成立します。両親にピロリ菌感染歴がある方は感染している可能性が高くなります(食器や箸の共有などによる経口感染など)。
ピロリ菌がいると胃の粘膜が傷つきやすくなり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因になります。
ピロリ菌がいると胃の粘膜が傷つきやすくなり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因になります。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌を薬で退治する治療です。除菌治療は、胃の病気を予防するためにとても大切です。
現在この治療法は保険適用があり、安全性が高いとされています。保険で認められている薬の組み合わせは2パターン(1次治療、2次治療)、処方する順番も決まっているため基本的にはどこで処方を受けても同じ組み合わせの薬が処方されます。
現在この治療法は保険適用があり、安全性が高いとされています。保険で認められている薬の組み合わせは2パターン(1次治療、2次治療)、処方する順番も決まっているため基本的にはどこで処方を受けても同じ組み合わせの薬が処方されます。
ピロリ菌の除菌治療の方法について
以下に、その治療方法を簡単にご説明します。
1. 内服治療
ピロリ菌の除菌には、以下の3種類の薬を1週間1日2回服用します。
- 抗生物質(細菌をやっつける薬)2種類:ピロリ菌を直接退治します。
- 胃薬(胃酸を抑える薬):胃酸を減らし、抗生物質が働きやすい環境を作ります。
2. 注意点
- 薬の服用中は副作用(下痢や軽い気分不良など)が出る場合がありますが、多くの場合は軽度で済みます。
- 指示通りに薬を飲まないと、菌が残ってしまう・耐性菌ができてしまう可能性があるため、治療を途中でやめないことが重要です。
- ペニシリンという抗生物質のアレルギーのある方は原則行えません。重症の皮疹が出現することがあります。
- ガイドラインでは除菌治療中の禁酒・禁煙を推奨しています。また、2次除菌中はメトロニダゾールという抗生物質が含まれるため、アルコールと併用すると副作用でアセトアルデヒドが蓄積しやすく、二日酔い様の症状が出現します。
3. 治療後の確認
ピロリ菌が除菌できたかどうかを確認する検査を行います。この検査には「尿素呼気試験」という検査を通常行います。
ピロリ菌除菌判定の尿素呼気試験について
ピロリ菌の除菌治療が終わった後に尿素呼気試験を行います。この検査は簡単で苦痛がなく、安心して受けていただけます。以下にその方法をご説明します。
尿素呼気試験とは?
尿素呼気試験は、吐き出した息(呼気)を使って胃の中にピロリ菌が残っているかどうかを調べる検査です。ピロリ菌がいる場合、胃の中で特定の反応が起こり、それが呼気から確認できます。この検査でピロリ菌が除菌されたかを判断できます。
検査の流れ
- 検査前の準備
- 検査を受ける時には、検査前5時間の絶食が必要です(通常、朝の検査であれば前日の夜以降、何も食べないようにして頂きます)。
- 一部の胃酸を抑える胃薬を飲んでいる場合は、検査結果に影響を与える可能性があるため(偽陰性)、検査前に中止する期間を医師が指示します。
- 検査の方法
- 検査当日、まずは普通に息を吹き込んで「最初の呼気」を採取します。
- 次に、「尿素(ユービット錠)」と呼ばれる特定の薬を飲んで頂きます。
- しばらく待った後、もう一度息を吹き込んで「2回目の呼気」を採取します。
- 結果の確認
- 採取した2回の呼気を専用の機械で調べ比較し、ピロリ菌がいるかどうかを確認します。この結果により、除菌治療が成功したかどうかがわかります。
注意点
- 検査は治療終了後、1〜2か月後に行います。これは、治療直後だと正確な結果が得られないことがあるためです。
- 除菌治療成功であれば、胃の病気のリスクを減らすことができます。
- ピロリ菌が残っている場合(除菌失敗)は、再治療(2次治療)を行うことができますのでご案内させていただきます。2次治療後も同様の検査で除菌治療の結果を確認します。
検査のメリット
尿素呼気試験は、ピロリ菌がいるかどうかを正確かつ簡単に調べる方法です。苦痛もなく、短時間で終了するため、多くの患者さんにとって負担の少ない検査です。
当院では、尿素呼気試験を安全・迅速に行っております。ピロリ菌除菌治療後のフォローも丁寧に対応いたしますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。尿素呼気試験は外注検査のため1~2週間後に結果を説明します。
ピロリ菌除菌治療の成功率について
ピロリ菌の除菌治療は、1次除菌治療(最初の治療)で多くの場合、成功します。その成功率は一般的に 約90% と言われています。ただし、治療の成功率は患者さんの体質やピロリ菌の薬に対する耐性(薬が効きにくい状態)などによって変わることがあります。
もし1次治療で除菌ができなかった場合、抗生物質の種類を変えた2次除菌治療を行います。この治療の成功率も約90%前後とされています。2次治療まで行うことで、ほとんどの患者さんがピロリ菌を除菌することが可能です。
もし1次治療で除菌ができなかった場合、抗生物質の種類を変えた2次除菌治療を行います。この治療の成功率も約90%前後とされています。2次治療まで行うことで、ほとんどの患者さんがピロリ菌を除菌することが可能です。
成功率に影響する要因
ピロリ菌の除菌成功率は、以下の要因によって左右されます。
- 抗生物質の耐性
最近は、ピロリ菌が抗生物質に耐性を持つケースが増えています。特にクラリスロマイシン(抗生物質)に耐性を持つ菌では、1次治療の成功率が低下する可能性があります。 - 薬の飲み方
決められた時間に正しく薬を飲むことがとても重要です。服薬の途中でやめてしまうと、治療の成功率が下がるだけでなく、耐性菌が生まれる原因になります。 - 胃の状態
胃酸が多すぎる状態だと抗生物質の効果が弱まるため、胃酸を抑える薬をしっかり使うことが治療成功のポイントです。
ピロリ菌を除菌することで得られるメリット
ピロリ菌を除菌することは、胃や体全体の健康を守るためにとても重要です。以下は、除菌を行うことで期待できる主なメリットです。
1. 胃がんのリスクを減らす
ピロリ菌は胃がんの大きな原因のひとつとされています。ピロリ菌を除菌することで、胃がんになるリスクを大幅に減らすことが期待されています。特に若い年代で除菌を行うほど、予防効果が高いとされています。
2. 胃潰瘍や十二指腸潰瘍・胃炎の予防・改善
ピロリ菌は、胃や十二指腸の粘膜を傷つけることで、潰瘍(かいよう)を引き起こす原因になります。ピロリ菌を除菌することで、これらの潰瘍が再発するリスクを大幅に減らすことができます。
3. 胃の不快症状の軽減
ピロリ菌は胃の中に慢性の炎症を引き起こし、もたれや痛み、食欲不振などの原因になることがあります。除菌により、これらの不快な症状が軽減されることが多く報告されています。
4.マルトリンパ腫の治療
胃に限局した早期の胃マルトリンパ腫(胃にできるリンパ系腫瘍)は除菌治療のみで消失することがあります。
5.特発性血小板減少性紫斑病の改善
血小板が減少してしまう原因不明の病気です。ピロリ菌が陽性の場合は除菌治療により改善が得られることがあります。
6. 貧血の改善
ピロリ菌は鉄分の吸収を妨げることがあるため、ピロリ菌が原因で鉄欠乏性貧血が起きることがあります。除菌を行うことで、鉄分の吸収が改善し、貧血が良くなるケースがあります。
7. 家族や周りの人への感染を防ぐ
ピロリ菌は主に口から感染します。家族間での感染が多いとされているため、自分が除菌をすることで、子供や孫など周囲の人への感染リスクを減らすことができます。
8. 長期的な健康への安心感
ピロリ菌を除菌することで、将来の胃の病気に対する不安を減らすことができます。特に、胃の病気になりやすい家系や胃がんのリスクが高いとされる方には、大きな安心材料となります。
除菌を検討するタイミング
ピロリ菌は、感染していても必ず症状が出るわけではありません。検査でピロリ菌がいると診断された場合は、症状がなくても除菌をすることをおすすめします。特に胃がんのリスクを減らすためには、胃の粘膜のダメージが少ないうちに早めの除菌が効果的です。
当院でのサポート
当院では、ピロリ菌の検査や除菌治療、治療後の確認検査まで丁寧に対応しています。また、ピロリ菌検査前後の胃カメラ検査も胃の状態によって適切な検査間隔を提案させていただきます。「ピロリ菌がいるかも?」と心配な方、「ピロリ菌を除菌するとどんなメリットがあるのか?」などのご相談もお気軽にどうぞ。あなたの健康を守るお手伝いをいたします。
ピロリ菌がいるかどうかは、血液検査や尿検査、息を使った検査(尿素呼気試験)などで簡単に調べることができます。ピロリ菌の除菌に成功すると、将来の胃の病気を予防する効果が期待できます。
原則ピロリ菌の検査は保険診療外の健康診断を除き、胃カメラ検査を先に行うことが必要となります(胃がんの除外のため)。保険診療ではピロリ菌の検査・除菌治療だけ施行するということは原則認められていませんのでご了承ください。
ピロリ菌がいるかどうかは、血液検査や尿検査、息を使った検査(尿素呼気試験)などで簡単に調べることができます。ピロリ菌の除菌に成功すると、将来の胃の病気を予防する効果が期待できます。
原則ピロリ菌の検査は保険診療外の健康診断を除き、胃カメラ検査を先に行うことが必要となります(胃がんの除外のため)。保険診療ではピロリ菌の検査・除菌治療だけ施行するということは原則認められていませんのでご了承ください。