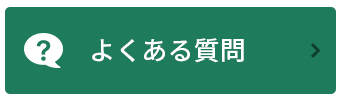熱中症について
熱中症の正しい知識と対策 〜高齢の方、持病のある方、小さなお子さんは特に注意〜
◆今年も暑い季節がやってきました
毎年、ニュースで「熱中症で搬送」という言葉を耳にします。私たちのクリニックにも
- 「めまいがする」
- 「頭がボーッとする」
- 「吐き気がある」
- 「なんとなくフラフラする」
◆熱中症は“命に関わる”病気です
熱中症は、高温・多湿環境で体温調節がうまくできなくなり、熱がこもってしまう状態です。
重症化すると、意識障害・けいれん・臓器障害を引き起こし、命に関わることもあります。
重症化すると、意識障害・けいれん・臓器障害を引き起こし、命に関わることもあります。
◆特に注意が必要な方
◆熱中症はどんな人でも起こりえる季節性の体調不良です。下記の方は特に注意が必要です。
- 高齢者(暑さを感じにくく、喉の渇きにも気づきにくい)
- 乳幼児(体温調節機能が未熟)
- 心疾患・糖尿病・高血圧などの持病がある方
- 利尿剤など水分バランスに影響する薬を飲んでいる方
◆医師がすすめる熱中症対策
1. 水分補給を“意識的に” 飲め!水分!!
2. 室内でも油断しない 測れ!室温!!
3. 外出時の工夫
4. 「暑熱順化」を意識
- 喉が渇く前に、こまめに水分補給
- 汗をかいたら塩分も一緒に(経口補水液やスポーツドリンクも◎)
- 適正な水分量はいつもと同程度の尿量が確保できること。汗の量にもよるが、目安は1日1.5リットルから
- コーヒーとビールは水分ではない!!
2. 室内でも油断しない 測れ!室温!!
- 室温は28℃以下を目安に空調管理、扇風機やエアコンを我慢しない
- 特に高齢者の一人暮らしは、「室内熱中症」に注意!
3. 外出時の工夫
- 日中の外出はなるべく避ける(午前10時~午後4時は特に危険)
- 吸湿速乾素材、日よけ帽子、日傘は夏の三種の神器!、黒い服はやめよう
- 日陰を選んで歩く・こまめな休憩と水分補給
4. 「暑熱順化」を意識
- 6~7月のうちから軽い運動や入浴で汗をかく習慣をつけ、暑さに強い体にする
◆何を飲む?
熱症対策、まずは「飲み物」から!
― 売っているもの・作れるもの、正しい水分補給を知ろう!
暑い日こそ、「何を飲むか」が命を守る!
熱中症の予防に一番大事なのは、“こまめな水分・塩分補給”。
でも、「水飲んでいるのに調子悪い…」という方、実は飲み方や飲み物選びに間違いがあるかもしれません。
― 売っているもの・作れるもの、正しい水分補給を知ろう!
暑い日こそ、「何を飲むか」が命を守る!
熱中症の予防に一番大事なのは、“こまめな水分・塩分補給”。
でも、「水飲んでいるのに調子悪い…」という方、実は飲み方や飲み物選びに間違いがあるかもしれません。
◆熱中症対策に向いている飲み物
◎市販のおすすめ飲料
| 飲み物 | 特徴・使いどころ |
| 経口補水液(OS-1など) | 脱水状態・軽度の熱中症の時に最適(塩分高め) |
| スポーツドリンク(アクエリアス、ポカリなど) | 普段の水分補給+軽い運動後に◎。やや糖分が多めなので飲み過ぎ注意 |
| 麦茶 | カフェインゼロで利尿作用なし。体を冷やす効果もあり、日常的におすすめ |
| イオン飲料(塩分入り) | 塩分チャージタブレットと一緒に活用するのも◎ |
◎自宅で作れる!かんたん熱中症対策ドリンク
【自作 経口補水液(目安:500mL分)】
- 水 … 500mL
- 食塩 … 1.5g(小さじ1/4弱)
- 砂糖 … 20g(大さじ2)
- レモン汁(好みで) … 少々
◆熱中症対策にならない・逆効果な飲み物
| 飲み物 | なぜNG? |
| コーヒー・緑茶 | カフェインによる利尿作用でかえって水分が出てしまう |
| アルコール(ビールなど) | 脱水を加速します。飲んでるいつもりが“出しているだけ” |
| 甘すぎる清涼飲料水 | 糖分過多で逆効果 |
飲み方のコツも大事!
- 「喉が渇いたときに一気飲み」はNG!
- こまめに、一口ずつ、回数を増やすのが鉄則!
- 目安:起床時・10時・昼・15時・入浴前後・寝る前に1杯ずつ意識
◆この症状が出たら、すぐに対処を
- めまい、ふらつき
- 頭痛、吐き気、こむら返り
- 全身のだるさ、汗が止まらない、または出ない
- 意識がぼんやり、呼びかけに反応しない
このようなときは、まず涼しい場所へ移動し、服をゆるめ、水分を摂取してください。
意識がない、反応が鈍い、吐いてしまうなどがあれば、すぐに救急要請を。
◆医師からのひとこと
熱中症は、「自分は大丈夫」と思っている人ほど危険です。
気温だけでなく、湿度・体調・年齢・服装・薬なども関係します。
異変を感じたら、無理せず早めに受診してください。
当院では、軽度の熱中症への対応・点滴治療も可能です。
「なんとなくおかしいかも?」という時点で、遠慮なくご相談ください。
意識がおかしい、動けない、という方は救急要請をしましょう。
気温だけでなく、湿度・体調・年齢・服装・薬なども関係します。
異変を感じたら、無理せず早めに受診してください。
当院では、軽度の熱中症への対応・点滴治療も可能です。
「なんとなくおかしいかも?」という時点で、遠慮なくご相談ください。
意識がおかしい、動けない、という方は救急要請をしましょう。