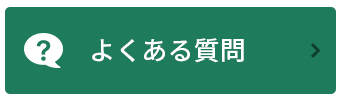医師が診療で大切にする「evidence」と「empiric(therapy)」とは?
診察のとき、医師は何を根拠に診断し、治療法を決めているのでしょうか?
その判断のベースには、大きく分けて 「evidence(科学的根拠)」 と 「empiric(経験的判断)」 の2つがあります。
その判断のベースには、大きく分けて 「evidence(科学的根拠)」 と 「empiric(経験的判断)」 の2つがあります。
■ evidence(エビデンス)=「科学的根拠に基づく判断」→科学の鉄板ネタ帳
先人や偉い学者さん達が作成した医学論文やガイドラインなど、大規模研究などで多くの患者さんのデータを分析して導き出された「標準的な治療法」、現在時点で正しいと考えられている治療法です。
再現性が高く、安全性、効果も期待できる、科学的根拠のある選択。田舎でも都会でも、病院でもクリニックでも同じ判断が出来るように。
→安心・安定・正統派の判断材料
たとえば
→ 再現性があり、多くの患者さんに安全で効果が期待できる方法です。副作用のない治療法、というわけではありません。
再現性が高く、安全性、効果も期待できる、科学的根拠のある選択。田舎でも都会でも、病院でもクリニックでも同じ判断が出来るように。
→安心・安定・正統派の判断材料
たとえば
- ピロリ菌感染による胃潰瘍には、3剤併用除菌療法が有効
- 痛み止めを長期内服する方の潰瘍予防にはPPI(プロトンポンプ阻害薬)が有効
→ 再現性があり、多くの患者さんに安全で効果が期待できる方法です。副作用のない治療法、というわけではありません。
■ empiric(エンピリック)therapy=「経験的判断・臨床的直感」
一方で、すべての症例に明確なevidenceがあるとは限りません。
初診で検査前に抗菌薬を使う、腹痛に対して一時的に制酸薬を使う、などの「経験に基づいた仮の治療」もあります。たくさんの似たケースを診てきた経験則に基づく判断、個々に合わせて柔軟なアプローチ。
→スピード感とリアル感が武器の即応力。
たとえば
初診で検査前に抗菌薬を使う、腹痛に対して一時的に制酸薬を使う、などの「経験に基づいた仮の治療」もあります。たくさんの似たケースを診てきた経験則に基づく判断、個々に合わせて柔軟なアプローチ。
→スピード感とリアル感が武器の即応力。
たとえば
- 「腹痛・下痢があり軽症の小腸炎の可能性が高い」→ 整腸剤で様子を見る
- 「下痢・発熱・血便があり、培養検査結果はまだ出ていないが、細菌性の可能性が高そうで具合が悪いので結果が出る数日後まで待っていられない」→ 予想される菌に効果のある抗菌薬を処方
■ 医師はこの2つをどう使い分けているか?
- まずはevidence(標準治療)をベースに考える
- ただし、すぐに検査ができない場合・軽症でそこまでは必要ない場合、具合が悪くすべての結果が出るまで治療が待てない場合、個々の患者さんの体質・背景を考慮する必要があるときは、empiric therapy(経験的治療)を組み合わせる
つまり
「科学的根拠」と「目の前の患者さんの状態」――その両方を大切にして診療しています。
同じ病状でも背景や年齢で処方する薬が違うことがあるのはそのためです。AIの発達でevidenceに則ったアドバイスを受けることは可能になってきていますが、状況による判断はまだAIだけでは困難です。
【まとめ】
- evidenceは“正解の地図”、方向を定めることに用います
- empiric therapyは“現場での勘と経験”、微調整に用います
- 医療はこの2つのバランスの上に成り立っています。
- いつかこれらもAIに取って代わる時が来るのでしょうか
市販薬や健康食品・サプリメント・民間療法など身の回りに健康になるため、と売られているツールは多数存在します。薬剤には基本的には良い作用(主作用)と悪い作用(副作用)が存在します、副作用のない薬剤は存在しない、と言われています。
基本的に医療機関で処方される薬にはevidenceが存在します(合う・合わない、副作用が出た、などはあり得ます)が、上記の物にはほとんど存在しないのが事実です。高額なものも販売されていますので使用する場合は良く検討してください。